前回の記事では「なぜ私たちはブックレビューを読むのか?」を論じました。
簡単に振り返ると
書籍購入の意思決定に伴う不安を和らげる
この効果を期待して読むのだと。
そしてブックレビューは「知の入り口」であること、著者・出版社・読者をつなぐ「架け橋」になるとの結論に至りました。
さて今回は「ブックレビューの本質とは何か」というテーマでお送りいたします。
ブックレビュー論 連載ポータル
はじめに
ブックレビューとは何かと問われたとき、僕はその役割は大きく分けて2つに整理できると考えています。
ひとつは「その本を買いたくなるように促すこと」、もうひとつは「まだ読んでいないにもかかわらず、少し“読んだ気分”に近づけてくれること」です。
- その本を買いたくなる
- その本を読んだ気にさせる
この2つの機能が重なりあう場所に、レビューという営みの”本質”があるのではないでしょうか。
「買いたくなる」という役割
まず前者の「買いたくなる」という機能は、分かりやすいものです。
読み手は、自分の時間とお金を投じる価値があるのかを見極めようとしている。その判断材料として、他者の視点を借りようとしているのです。
ただしそれは決して「煽り」や「宣伝」のことではありません。本の魅力や射程の広さ、そして言葉の温度を、誠実に伝えようとする営みであるべきです。
ここに、レビューが本来持つ文化的な意味が宿りはじめます。
「読んだ気分になる」という役割
一方で、レビューにはもうひとつの顔があります。
それが「読んだ気分になる」という働きです。本を手に取る前から、その思想や景色の輪郭が、少しだけ見えてくる。レビューは、読書という体験の手前に置かれた“予告編”あるいは“イントロダクション”のような存在だといえるでしょう。
つまりレビューとは、書籍と読者のあいだに“橋”を架ける仕事なのです。
価値の媒介としてのレビュー
だからこそ、要約や引用の羅列はレビューとは呼べません。ましてや、目次・著者プロフィールの丸写しに至っては論外でしょう。そこに書き手の視点や理解が介在しなければ、それは情報の複製に過ぎないからです。
レビューは「価値の媒介」であり、読み手と本との出会いを取り持つ通訳のような役割を担っています。だからこそ、レビューを書くという行為には、いつも静かな責任が伴います。
本を書いた著者、出版した出版社、そしてそれを読むかもしれない読者。そのすべての人に対して誠実でありたい。
レビューはその真ん中に位置しながら、誰かの人生の数時間をそっと導いていく文章なのです。
この2つの機能──
「買いたくなる」
「読んだ気分になる」
それらを意識したとき、レビューは単なる感想文を超えて、欠くことのできない要素「本質」に迫る文章になるのだと思っています。
次回は「論旨が曖昧なレビューは機能しない」
前述した二つの要素を加味するとレビューが果たすべきは「読者の意思決定と理解を支える」ことに集約されます。
言うまでもなく、論旨が曖昧なレビューは、その役割を担いきれません。
ではなぜ、“何を伝えたいのか分からない文章”は機能しなくなるのか。第3回では、この問いに向き合っていきます。
あわせて読みたい
当ブログサイト「THINK INK NOW」ではこれ以外にも読書関連の記事を多数ご用意しております。この機会にぜひご覧ください。

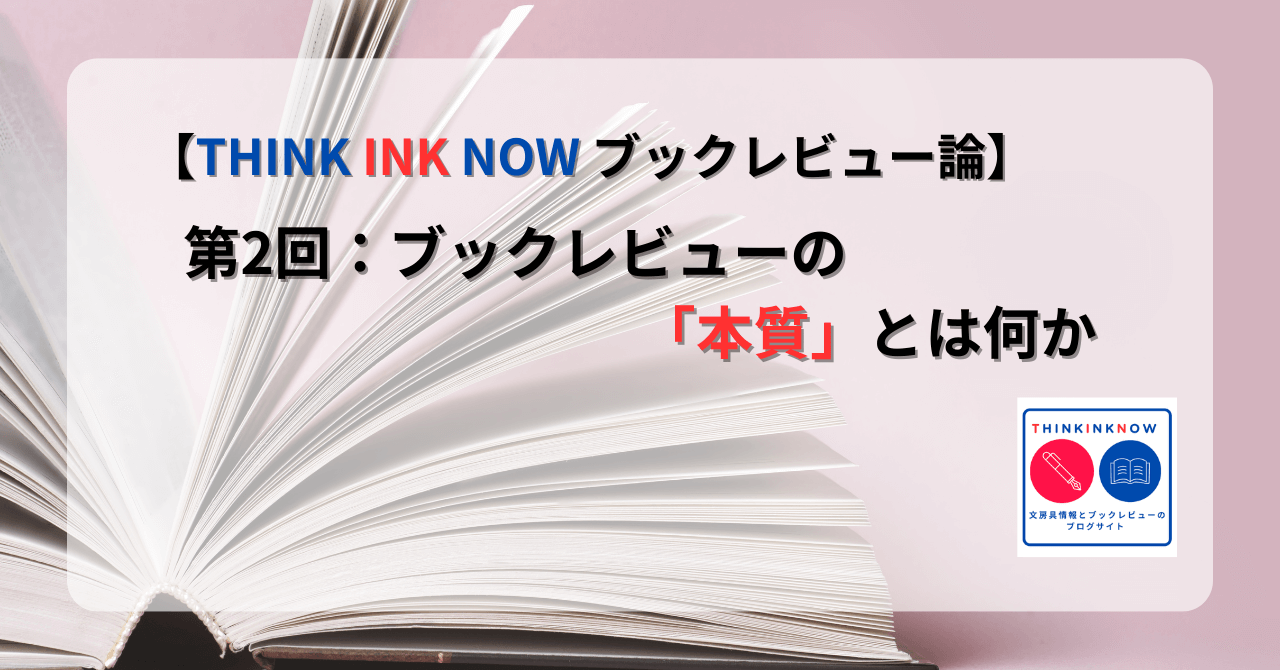






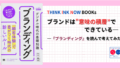
コメント