この記事を書いたのは、ある新書の一文がきっかけだった。
きっかけとなったのは「新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと」 (斉藤友彦著/集英社新書)である。
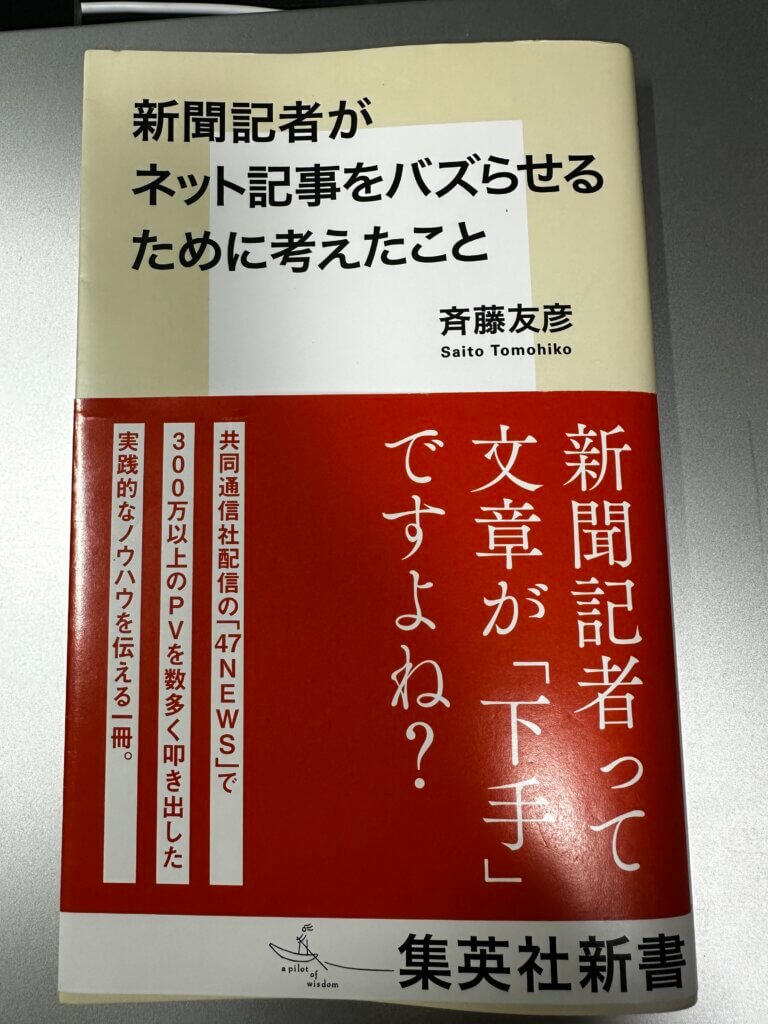
このキャッチ―なタイトルからは想像出来ないほど、発信のヒント満載である。
マクラも早々にして、さっそく本編に進んでいこう。
『新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと』(斉藤友彦著/集英社新書)をAmazonで見る。
はじめに──なぜ「共感」という言葉が気になったのか
最近、ネット記事や SNS を眺めていると、「自分事で語る」「体験を語る」文章が、以前にも増して目につくようになった。
それは単なる流行なのか、それとも、読む側の感覚が変わってきた結果なのか。
冒頭で紹介した書籍『新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと』で、著者は「共感」を次のように定義している。
共感 とは、他人 が 経験 したことを、まるで 自分 が 経験 したことであるかのように、あるいは 自分 の 家族 など 近 しい 人 が 経験 したことであるかのように 感 じされることである。であるなら 最近 よく 聞 く 言 い 回 しの「 自分事」 の 記事 にできれば、もっとよく 読 まれるようになるのではないか。「新聞記者 が ネット 記事 を バズ らせるために 考 えたこと」( 斉藤友彦著 / 集英社新書)
この一文を読んで、とても肚落ちした感覚があった。そして同時に、「最近よく聞く“自分事の記事”が読まれる理由」が、少しだけ輪郭を持ったように思えたのだ。
『共感』とは「感動や同情」とは違うもの
では、なぜいま「自分事」の文章が増えているのだろうか。理由のひとつは、情報が過剰になりすぎたことだと思う。
世の中には「正論」「データ」「まとめ」これに類する情報が溢れている。そんな環境の中で、「正しいこと」よりも「その人がどう考えたか」が、文章の説得力を持つようになってきた。
これは、文章の劣化ではなく、読む側が“他人の思考の厚み”を感じ取ろうとしているという変化なのかもしれない。
「正しい」ことも重要ではあるが、そのうえで、血の通った人間が持つ感情を受け取りたいとの表れだろう。
共感は「狙って作れるもの」なのか
さりとてここは、少し冷静になりたい。共感が大事だと言われるようになると「共感を狙った文章」が量産されるのではなかろうか。
- 過剰な告白
- 不幸の切り売り
- 過酷で凄惨な体験談
たしかに、このような文章はセンセーショナルに伝わり、注目を集めるかもしれない。しかし、それは本当に共感なんだろうか。
共感とは、テクニックとして“作る”ものではなく、書き手の生活や思考が、結果として滲み出たときに生まれるものだと、僕は考える。
「自分の言葉」でしか書けない文章がある
共感が生まれる文章には、共通点がある。それは、
- 無理に結論を急がない
- 読み手を操作しようとしない
- 書き手がそのテーマと長く付き合っている
ということ。
読書の積み重ね、考え続けてきた時間。そして、うまく言葉にできなかった経験。そうしたものが幾重にも積み重なったとき、文章は「情報」ではなく「体験の共有」に近づいていく。
それは、誰にでも刺さる文章ではないだろう。けれど、「分かる人には、確実に届く文章」になるのではないか、と。
共感は集めるものではない
そう考えると、共感は集めるものではない。ましてや、演出するものでも、数値化できるものでもない。
書き手が、自分の言葉で考え続け、自分の手で書いた結果として、読み手の中に、静かに生まれるものである。
読まれない日も、反応がない日もあるだろう。僕みたいに、しがない野良に生息するブロガーの文章など、読まれなくて当然だ。
それでも、「これは自分の言葉だ」と言える文章を残していくこと。それが、長く読み続けられる文章へ、一見遠回りにも見えるが、もっとも確実な道なのではなかろうか。
おわりに──今日もこうして拙文を綴っている
今回の記事を書くきっかけをくれた書籍『新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと』は「こう書けばバズる」とは言ってない。
長年の記者生活で習性となり、新聞記事の型にハマった文章をネット記事で読まれるためにどうしたらいいかと悪戦苦闘する様を書いている。
むしろ、書くことに関わる人間に「それでも、文章をどう書くのか」を問い返してくる内容だ。
僕は書くことを信じる。僕は言葉の力も信じる
だから工夫を重ね、文章を磨き、想いを伝えたい。それを実感することは、書き手として何よりもうれしいからだ。
だから、僕は今日もこうして拙文を綴っている。
あわせて読みたい
文房具情報とブックレビューのブログサイト「THINK INK NOW」ではブックレビュー記事を多数掲載しております。この機会にぜひご覧ください。

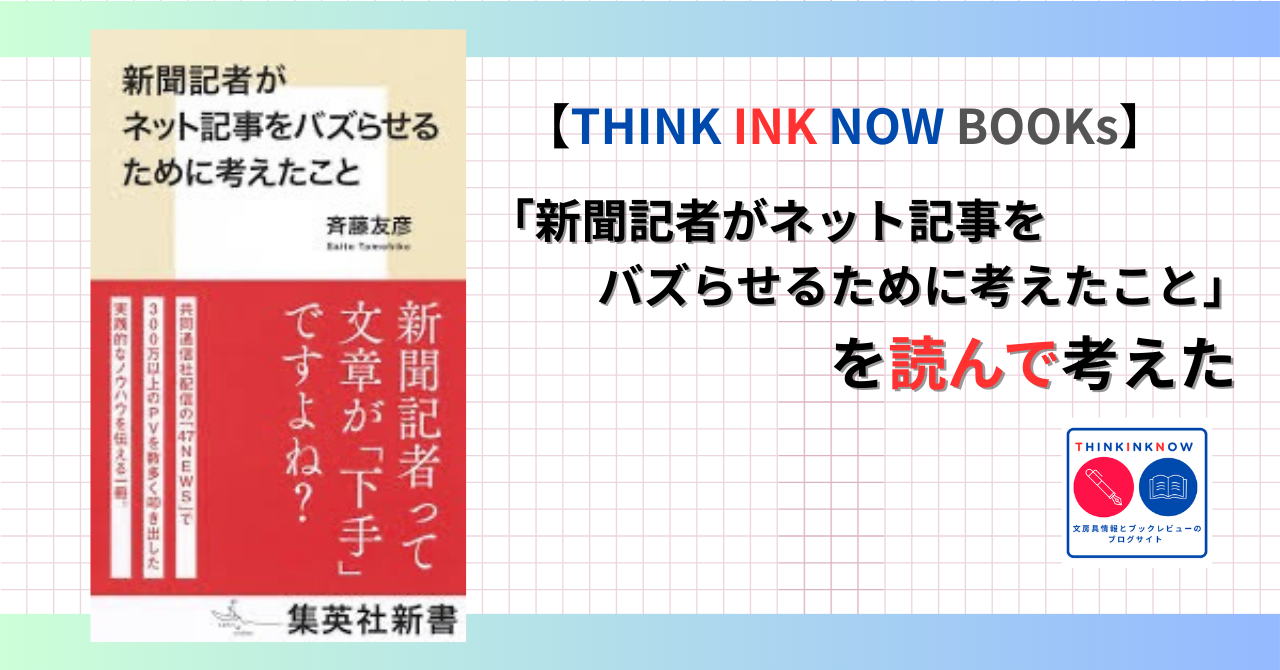
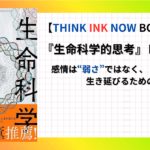
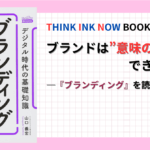

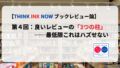

コメント