「ネタバレ」という言葉は、何を誤魔化しているのか
ブックレビューに限らず、映画紹介でもそうだが、その手の文章には必ずついて回る言葉がある。
「ネタバレ」
書く側も、読む側も、この言葉をまるで触れてはいけない地雷のように扱っている。だが僕は、ずっとこの言葉に違和感を覚えてきた。
なぜなら──ネタバレという言葉そのものが、書評の思考を止めてしまっていると感じるからだ。
ネタバレは「内容を言うこと」ではない
まず整理しておきたい。そもそも詳細なブックレビューは、読者からその本に対する興味を奪うものなのだろうか。
その前提が成立するとして、いわゆる「ネタバレ」が致命的になるのは、プロットやトリック、あるいはオーラスの結末など、意外性そのものが作品の価値を支えている場合だ。
ミステリーやサスペンスでは、その開示にならないような慎重さが求められるだろう。しかし、文学作品、思想書、評論、ノンフィクション、ビジネス書の多くはどうだろうか。
内容を事前に知ったからといって、読む価値が大きく損なわれる本は、実はそれほど多くない。
それにもかかわらず、僕たちはすべての本に対して、一律に「ネタバレ禁止」という空気を適用してしまっている。ここに、最初の歪みがある。
ネタバレ恐怖が生む、読書体験の劣化
ネタバレを過剰に恐れる文化は、読書を次のようなものに変えてしまう。
- 初見の驚きがすべて
- 一度読んだら価値が下がる
- 結末を知ったら損をする
これは、読書を消費イベントとして扱う態度だ。
しかし本来の読書体験は、そうではない。再読によって意味が変わり、引用によって輪郭が立ち、解釈の微調整によって、より理解が深まっていく。書籍に表されている言説を、より精密に読み直せるようになる。
しかし、ネタバレの恐怖は、読書を「一回性の娯楽」と決めつけ、そこに閉じ込める装置になっている。
ブックレビューが本当に開示すべき情報とは
では、書評は何を伝えるべきなのか。
僕はこう考える。書評とは「何が起きるか」を伏せる行為ではない。「読むことで、何が起きうるか」を示す行為だ、と。
- 価値観が揺さぶられる
- 読み進めるのが精神的にきつい
- 前提知識がないと置いていかれる
- 読後、しばらく考え込むことになる
これらはネタバレではなく、むしろ読者への誠実な情報提供ではないだろうか。
まとめ──「ネタバレ」という言葉が隠しているもの
結局のところ、「ネタバレ」という言葉は、何を誤魔化しているのか。
それは、書き手の覚悟と、読み手の主体性だ。どこまで示すのか。どこから読者に委ねるのか。その線引きを考える代わりに「ネタバレだから」という言葉で思考を止めてしまう。
それは安全ではあるが、必ずしも誠実な態度とは言えない。
ネタバレを恐れるあまり、レビューの多くは本の核心ではなく、安全圏だけをなぞるものになりがちだ。
そもそもレビューとは、読者を守るための柵ではない。
読むことで何が起きうるのか。そのリスクと可能性を、あらかじめ提示すること。お金と時間を差し出して、何が得られるかを暗示すること。
それが、ブックレビューという行為の本質だと、僕は思っている。
あわせて読みたい
ブックレビューのブログサイト「THINK INK NOW」では連載企画の「ブックレビュー論」、ブックレビュー記事の「アーカイブ」、それぞれの「ポータル」からシリーズ全作品を読むことが出来ます。この機会にぜひご覧ください。




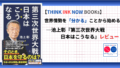
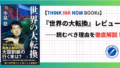
コメント